A プロローグ
新しいことを考える時みなさんは何から手を付けるでしょうか。
それが町や暮らしに関わることならやはり歴史を紐解いてみたい、そのように思われる方も多いことでしょう。ただ映像作品にする場合、「絵」をどうするかが大きな課題です。その上、じっくり話題にできる時間がない時、映像作品は撮影できる対象に大いに頼ることになります。
大仏さんは、高岡での映像製作に無くてはならない存在でもあるのです。
高岡大仏
 高岡大仏まず冒頭に何を持ってくるか、映像作品のトップカットは、全体を表現するか、それとも意表を突く一点に集中すべきかなかなかに迷うところです。
高岡大仏まず冒頭に何を持ってくるか、映像作品のトップカットは、全体を表現するか、それとも意表を突く一点に集中すべきかなかなかに迷うところです。
しかし迷ったら大仏さん!……それが高岡なのです(?)
冒頭のナレーションは以下の通りです。
(ナレーション原稿には、頭に「N」があります)
N「街中で、直径11メートルもある円光背を背負うのは、高岡の大仏さん、……高岡大仏です。」
 11メートルもある円光背、おそらく他に類を見ないのでは……?言うまでもなく、高岡大仏は高岡だけに存在し、
11メートルもある円光背、おそらく他に類を見ないのでは……?言うまでもなく、高岡大仏は高岡だけに存在し、
そして、大きくて、懐の深いものだと私たちは思っています。
さらに言えば、もともと高岡大仏(三代目)は鋳物の町高岡を象徴するために市民を巻き込んで大変な思いをして誕生していることこそ重要だ考えます。
大きな円光背だけでなく、彼はそういう歴史を背負っているのです。
何しろそのお顔には市民の大切な日用品まで鋳込まれているのですから。
(「高岡大仏と高岡市生産共進会」を参照下さい)
 毎年9月22日に行われる「お身ぬぐい」(画像は平成22年9月22日撮影)毎年行われる高岡大仏恒例の行事に「高岡大仏まつり」があります。
毎年9月22日に行われる「お身ぬぐい」(画像は平成22年9月22日撮影)毎年行われる高岡大仏恒例の行事に「高岡大仏まつり」があります。
例年天候が不順で朝から雨の日が多いのですが、
なぜか お身ぬぐい の時間帯はだいたい小雨以下です。これも大仏さんのご利益でしょうか……。
(平成22年度については、「第42回 高岡大仏まつり」を参照下さい)
以下のナレーションが続きます。
N「焼け落ちた木像を、市民の祈りが
鋳物の技術で大きな銅像に甦えらせました。」
N「しかし、このお顔に込められたのは人びとの願いばかりではありません。」
N「何と!
金盥(かなだらい)の破片やら、メガネの縁、果ては 煙管(きせる)の雁首(がんくび)に至るまで……、
『金という字の付くものならなんでも』一緒くたに 鋳込まれていたのです。」
N「木像だった計画を銅像に変更。
それによる巨額の再建費集めの一環として考え出されたのが
市民からの"現物寄進"というアイデアだったのです。」
N「それほどにこだわる "ものづくりの町" 高岡とは……。
いったいどのような足跡を辿ってきたのでしょうか。」
メインタイトル
 二上山から南西を望む
二上山から南西を望む
メインタイトルまでの映像撮影は二上山から行いました。ここからなら市内福岡町方面に続く小矢部川流域が(左画像)、
日本海に突き出た吉久や六渡寺(庄内町)方面が(左下画像)一望できますし、
高岡の市街地も臨めます(下画像)。
さらに、目を凝らしてみると庄川に架かる新幹線(工事中の橋脚)も見て取れる場所です。
 二上山から東方を望む
二上山から東方を望む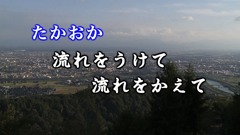 二上山から南方を望む
二上山から南方を望む
